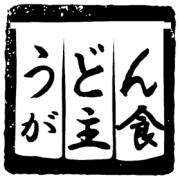“日本三大うどん”と言えば必ず名前が挙げられる「讃岐うどん」と「稲庭うどん」。
どちらも知らない人はいない有名なうどんですが、その違いはどこにあるのでしょうか?
讃岐うどんと稲庭うどんの違いを検証してみましょう。
讃岐うどんとは
讃岐うどんには香川県が定めた「定義」があります。
粉の指定こそありませんが、加水量や食塩量、ゆで時間などに細かいルールが存在します。
(1)香川県内で製造されたうどん
(2)手打または手打式、手打風に加工したもの
(3)小麦粉重量に対しての加水量が40%以上のもの
(4)小麦粉重量に対しての食塩量が3%以上のもの
(5)2時間以上熟成させること
(6)ゆで時間を約15分とし麺を充分アルファ化させていること
尚、讃岐うどんの定義は香川県内のみで通用するルールなので、他県に展開しているチェーン店の「讃岐うどん(さぬきうどん)」に定義はないそうです。
稲庭うどんとは
稲庭うどんは秋田県南部に古くから伝わる、手延べ式製法による乾麺タイプのうどんです。
冷や麦よりは太く、平べったい麺が特徴です。寛文年間以前に秋田藩稲庭村で作られてたとされ、少なくとも江戸時代にはその存在が確認されています。
一般的には乾麺で流通していますが、地元である秋田県南部や秋田県のアンテナショップなどでは半生タイプの面も入手できます。
2007年には農林水産省より「農山漁村の郷土料理百選」にも選ばれています。
讃岐うどんと稲庭うどんはココが違う!
では具体的に讃岐うどんと稲庭うどんはどこが違うのでしょうか?
その違いを見てみましょう。
・製麺方法が違う
讃岐うどんと稲庭うどんではそもそもの製麺方法が違います
【讃岐うどん】
定義通りの水と塩で練り上げた小麦粉の生地を、薄く伸ばして折りたたみ、包丁で麺線状に切る「切り麺」タイプ
【稲庭うどん】
太く切った麺に縒り(より)を掛けながら、細く引き伸ばして作る「手綯い(ない)」タイプ
・食感が違う
【讃岐うどん】
気泡のないエッジのたった四角い切り口の面が特徴で、噛んでモチモチ感を楽しめます。
【稲庭うどん】
細く引き伸ばして作るため、麺に気泡ができ、絹のようななめらかな口当たりとのど越しが特徴。
・おすすめの食べ方が違う
【讃岐うどん】
茹で上げた麺を冷水で締め、ネギや大根おろしなどの薬味と共に、だし醤油やだしをぶっかけて食べる「ぶっかけ」がおすすめ。
【稲庭うどん】
茹で上げた麺を冷水で締めた冷たい状態のざるうどんを麺つゆで頂く、シンプルな食べ方がおすすめ。
いかがでしたでしょうか?
讃岐うどん、稲庭うどん、それぞれに特徴があります。
どちらのうどんも非常に美味しいのでそれぞれ食べ比べてみましょう。
うどんが主食プロデュースの半生讃岐うどん
 ご購入はこちら
ご購入はこちら